機能と効用
1.はじめに
古代ギリシャでは歯や口の中をきれいにするためにマスティツクの樹脂を噛み、中南米に住んでいたマヤ族は約3,000年前からサポディラの樹液を固めて、歯や歯茎を丈夫にするために噛んでいたといわれている。このようにチューインガムの起源は咀嚼力の強化や口腔内の浄化にあるが、これを科学的な研究により、噛むという行為が人間にとっていかに大切であるかを初めて証明したのがコロンビア大学のH・L・ホーリングワース教授である。※1
咀嚼は、全身的な自立神経系の反応を伴い代謝活動が増加し、また口腔内組織が刺激を受け、唾液が分泌されて口中が浄化されたり、口腔内組織や脳への血流変化を生じさせる。
このように、チューインガムには本来の噛むという機能によって、図1に記した多くの効用性が現在までに立証されている。系統的には生理面、心理面の賦活と口腔内機能の二つに大別されるが、このチューインガムの咀嚼による本質を活かし、さらに効能性を高めるために機能性素材を添加することによって各々の品質特性を推しだした各種効能ガム商品が上市されている。
本稿では、はじめにガムの咀嚼による顎の発育への影響、口腔内および脳、生体系へ及ぼす影響などについて最近まで明らかにされた内容に触れ、つぎに各種機能素材を利用した効能ガムについて述べる。
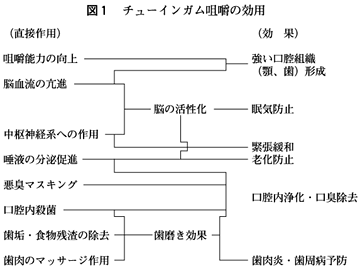
2.ガムと咀嚼機能
一般に咀嚼とは、われわれが食物を摂取してこれを粉砕し、唾液と混ぜ合わせ、柔らかく擦りつぶす生理的作用をいうが、これは単純なものではなく、口腔内の多くの器官や組織の複雑な機能が調整されて行われるものである。
(1)咀嚼力の強化
チューインガムを噛むと咀嚼力が向上することは経験的にわかっていたが、これを実験で科学的に裏づけるデータはなかった。最近、食生活の変化によって硬いものが食べられないとか、食事にかかる時間が長いなど、小児の咀嚼発達が遅れているのではないかという問題が生じている。そこで、このような咀嚼運動が充分に行われていないと考えられる幼児に、硬さ調整したチューインガムを用いて咀嚼運動の訓練を行った。
その結果、訓練開始後三ヵ月目には訓練前と比較して、最大咬合力が約二倍に増加することが認められた。※2これは、チューインガムを用いた咀嚼訓練が、咀嚼機能の発達を促す効果的な方法であることを示している(図2)。
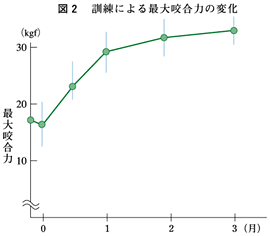
また、チューインガムによる訓練開始後、咀嚼力の向上が確認された子供の母親に対するアンケート調査を行った結果、食べる量が増えたこと、食事に要する時間が短縮したことおよび今まで見向きもしなかった食物に興味を示すようになったことなどもわかった。
同じチューインガムを用いた咀嚼訓練をナイジェリアの幼児について行った結果、二週間で咬合力は約10%しか増加しなかったが、これは通常かなりの咀嚼力で噛んでいるためであろう。これに対し、日本の幼児は顎のもてる力を充分に出しきっていないことが指摘され、咀嚼訓練を行えば、咀嚼能力はさらに向上することが確認された。
(2)唾液の分泌促進
唾液には人間の健康に必要な生命の根源物質である酵素やホルモンなどがたくさん含まれている。ご飯やパンをよく噛んで食べると口中が甘くなるのは、唾液中に含まれているアミラーゼという酵素が澱粉を甘い麦芽糖などに変えるからであることがよく知られている。
また、唾液の中にはパロチンという唾液腺ホルモンが含まれており、これは若返りホルモンといわれ、いちばん老化の激しい歯、毛髪、生殖器などの機能維持に効果があるといわれている。
チューインガムの咀嚼時には多量の反射唾液が分泌されることから、口腔の二大疾患である齲蝕(うしょく)と歯周病の予防と関連して、近年種々の研究がなされている。一般に、食物の咀嚼時にはチューインガムに限らず唾液が分泌され、その滑剤作用により、咀嚼動作を円滑にさせている。唾液の役割にはそのほかに、口腔粘膜の保護作用、口腔の浄化作用、そしてpH変化を最小に保つ緩衝作用などがあり、口腔各組織の生理機能に強い影響を及ぼしている。
ところで、ガム咀嚼による唾液分泌促進およびpH緩衝作用を確認するため、三種類の香味の異なる(ペパーミント、酸入りと酸なしフルーツ)チューインガムと、糖や香料を含まないチューインガム(ガムベース)について咀嚼時中の唾液の分泌量とpHの変動を調べたところ、図3、および図4のようになった。
すべてのサンプルにおいて咀嚼中の唾液分泌量は増加し、30秒から3分後までが最も多量となった。ガムベースと他のチューインガムを比較した場合、咀嚼直後から約三分後まで後者はさらに唾液の分泌量が大となり、それ以後はほぼ同程度となった。これは咀嚼以外にチューインガムに含まれる糖および香料も唾液分泌を増加させる因子になっているからであろう。
またpHの変化は、酸入りチューインガムを除き、咀嚼直後から上昇して比較的高いpHレベルを保った。酸入りチューインガムの場合は咀嚼直後に下がったが、まもなく回復して他とはぼ同じレベルを保った。※3これは唾液の緩衝作用による現象であると考えられる。
以上のようにガム咀嚼には、唾液分泌を促し、pHの緩衝作用があることが確認された。
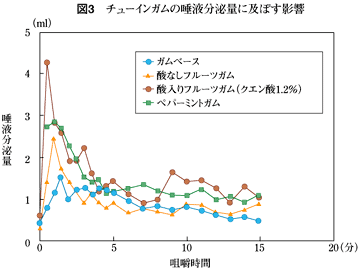
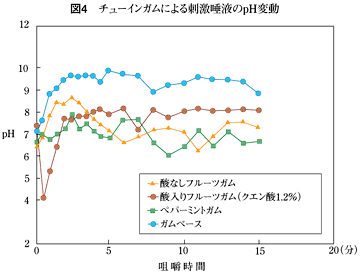
(3)脳血流量の増加
最近の研究により、咀嚼と全身の健康とりわけ脳機能の発達との依存性が強調され始めている。
咀嚼は歯や顎を動かす単純な随意運動ではなく、脳において高度な統合機能が関与して成立する運動であるといわれている。たとえば動物実験では、イヌの前頭葉外側下部の眼窩回の電気刺激で、顎のリズミカルな運動が起こることが知られており、咀嚼中枢と呼ばれている。※4,5ラットを用いた行動学研究では、固形食で飼育した群は、粉末食で飼育した群よりも迷路実験の成績が良いと報告されている。※6また、幼堆園児の咀嚼能力と知能指数および数唱テスト得点相関について調査したところ咀嚼値、咬合力が高い園児は、低い園児と比較して指数および得点が高くなる傾向が見られたとの報告もある。※7,8
これらの研究内容は、よく噛むことが栄養面で有利な効果をもたらすだけではなく、咀嚼運動自体が脳に対して何らかの良い影響を及ぼすことを示唆している。
そこで、脳機能の発達の基礎要因となる脳血流量と咀嚼との因果関係の実態を明らかにする目的でポジトロンCTと酸素-15標識水を用いてチューインガム咀嚼時の局所脳血流量の変化を画像解析した。
ポジトロンCT(positron emission tomo graphy’ PET)は、核医学診断法のひとつで陽電子(ポジトロン)を放出する放射性同位元素で標識した放射性薬剤を被験者に投与し、その臓器内分布をPETカメラで断層画像に撮影する検査法である。※9放射能の臓器内分布は臓器の局所機能を反映するので、血流や代謝など生理学的、生化学的機能を抽出できる。局所脳血流の測定には、放射性薬剤として、酸素-15標識の水(H2O15)が用いられる。酸素-15は半減期が2分と非常に短いので、10~15分たてば放射能は減衰してなくなる。
実験は20歳から85歳までの30名について、MRI(磁気共鳴断層撮影)と酸素-15標識水少量静注後、PET(陽電子放出断層撮影)で脳血流量とその領域を同定した。被験者にはチューインガムを咀嚼させたときの脳の画像から安静時の画像を差し引きして血流量の変化を計算した。
結果は両側の一次運動感覚野の下部領野に20~40%の有意な血流増加がすべての被験者においてみられた(図5)。そのほかに有意な血流増加が大脳基底核や小脳にもみられた。また脳外部領域での、両側の側頭筋部に100以上の血流の増加がみられた。※10側頭筋部の血流増加はガム咀嚼時の活発な咀嚼筋活動を反映したものと考えられる。
局所脳血流の増加は、咀嚼システムの効果器サブシステムから感覚入力サブシステムを介して脳に送り込まれる咀嚼感覚情報を、フィードバックする大脳の感覚運動神経細胞の代謝活動の亢進がつくり出す炭酸ガス分圧の高まりによって、そこの毛細血管腔を拡張させた結果惹起されたものと思考されている。
からだの発育期での脳血流の増加現象は、脳の機能的発育に大きな役割を果たすと考えられている。幼少時からよく噛む食生活が子供の脳やからだの健康づくりに大切であることがいえるであろう。
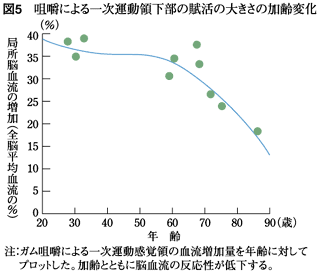
(4)全身への影響
チューインガムの咀嚼には覚醒作用、※11やリラックス効果※12があるといわれている。これらの二つの作用は相反する関係にあり、チューインガムを摂取するオケイジョンで効果も異なり、ガムの咀嚼がもつ不思議な二面性といえる。
ところで、チューインガムによる咀嚼運動によりこれらの効果が生じることは、咀嚼時のエネルギー需要量変化に応じて覚醒やリラックスに関連する生体の反応性も変化すると考えられる。
そこで心拍数(HR)、血圧(収縮期:SBP、拡張期:DBP)、酸素摂取量(VO2)、脳血流量、鼓膜温、皮膚温や下垂体-副腎および交感神経由来のストレスホルモン(副腎皮質刺激ホルモン:ACTH、アドレナリン:Ad、ノルアドレナリン:Norad)の血漿濃度変化を指標として、ガム咀嚼時および硬さの異なるガムを咀嚼した場合の全身への影響を調べてみた。※13
被験者は17~46歳の健康人男女15名を対象とし、実験結果は以下のようになった。
心拍数(HR)は咀嚼開始と同時に有為に上昇し、咀嚼終了と同時に急激に減少した。咀嚼時のHR上昇程度はガムの硬さに依存した。また毎分換気量(VE)やVO2もガムの硬さに依存して上昇したが、VO2は硬いガムが高く、軟らかいガムで少なくなる傾向にあったものの、VEの変化ほどガムの硬さとの関連は明確ではなかった。いずれのガムもHR同様咀嚼5分以降VE、VO2ともに上昇が僅少となり、咀嚼終了5分後は咀嚼前値に回復した。血圧もHRやVE、VO2とほぼ同様の動態を示した。
一方、鼓膜温は咀嚼開始と同時に有意な減少を示して咀嚼終了後回復し、またドップラー法で測定した総頸動脈血流はガム咀嚼によって増加した。この結果は、ガム咀嚼により脳血流量が増加していることを示唆するものである。
チューインガム咀嚼後のACTH、Ad、Norad濃度については、図6のようにガムの硬さに関係なくいずれも咀嚼後低下する傾向にあった。
ヒトに心理的ストレスや騒音刺激を与えると、血漿コルチゾールやアドレナリン、ノルアドレナリン濃度が上昇する。またラットに対し皮膚を鉗子でつまむ侵害刺激を与えると、副腎皮質活動が高まりカテコールアミン分泌が増すが、ブラシで毛をこすったり、さすると逆に副腎神経活動は一過性に低下し、カテコールアミン分泌も減少することが報告されている。ラットにとって前者は侵害刺激となり、後者はストレス解消になっていると考えることができる。
このようなストレスホルモンといわれるACTH、AdおよびNoradは、ガム咀嚼によって分泌が抑制されるものと推察される。
以上のように、チューインガムの咀嚼には口腔内のみならず、全身にもいろいろな影響を及ぼすことがわかってきた。咀嚼がからだの調整機能に与える影響については、さらに解明されていくものと思われる。
ところで、ガム咀嚼によって血圧が上昇したことから、咬筋活動(咀嚼運動)は末梢細動脈血管に分布する交感神経系の興奮を促進することが考えられる。一方、ガム咀嚼時の内分泌反応から推察すると、ガム咀嚼によって交感神経系の活性が抑制されたことが推刺される。
この相反する結果は、チューインガムのもつ覚醒作用とリラックス効果の相反する作用をそれぞれ裏付けてはいる。しかし生理、心理的立場から今後さらに詳細な研究を進めて明確にする必要もあるだろう。
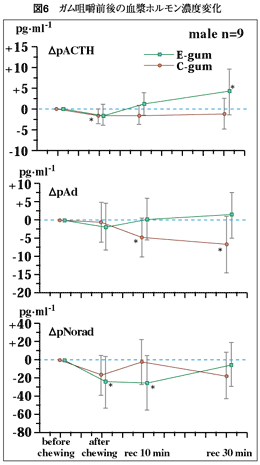
3.各種効能ガムの素材と機能
(1)各種効能ガムの素材と機能(1)
チューインガムの咀嚼によって眠気防止効果、覚醒効果が現れることは、これまでの実験によって科学的にも明らかになってきている。一般に眠気防止、覚醒効果の試験は、脳波や心拍数、フリッカー値などの測定によって行われている。
単純作業時における意識レベルに対するガム咀嚼の効果として、内田クレペリン作業を参考に作成した一位数加算作業による実験結果がある。※14この結果、脳波では個人差がかなり認められるものの、浅い眠りのときに出現するθ(シータ)波の出現率がガム咀嚼により抑制され、覚醒レベルの低下の抑制が認められた(図7)。また自律神経系の緊張指数である心拍数変動についても高く、正答数の増加がガム使用により認められた。このように作業の単純化に伴う意識レベルの低下が、ガム咀嚼により抑制されることが実験的に確認されている。
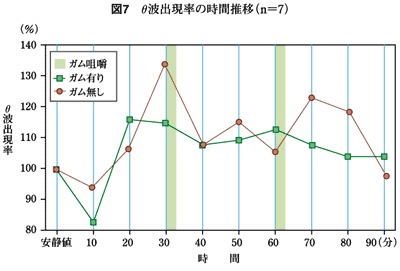
さて、このチューインガムの機能に強力ミントと効能物質を配合し、眠気防止機能を高めたガムが製品化されている。使用しているカフェイン、菊花エキス、イチョウ葉エキスの三つの効能物質について触れてみる。
カフェインはコーヒー豆から熱湯抽出、結晶化されたものを利用しており、さらにカフェイン含量の高いガラナエキス(原産はブラジルで古来より不老長寿の名薬として疾病に用いられていた)も添加している。
カフェインは眠気防止に効くことは広く知られているところであるが、その薬理作用は中枢神経系、心臓、循環系、その他に分けられ、かなり広範囲に及んでいる。中枢神経系に対しては少量で興奮作用を示し、最初に大脳皮質、次いで延髄に作用が及ぶ。
菊花エキスの原料、菊花は古くから漢方処方としてとくに眼科領域で広く利用され、また清涼飲料として喫茶用(中国)に利用される経験が長いなど、観賞花のみならず医食に密接に関係を持っている。
その菊花の抽出物(エキス)は局外生規キクカの中切を水蒸気蒸留により抽出、減圧濃縮して得られる。その精油成分はボルネオール、カンファーなどで、カンファーには中枢神経全般の興奮作用があり、これにより大脳皮質が興奮され、眠気や疲労感を取り除く効果がある。
この菊花エキスには毛細血管の抵抗力の増強作用があり、これにより血液循環が良くなり、とくに眼精疲労を防ぐ働きがある。さらに視神経のみならず全身の血液循環を改善し眠気や疲労の回復にも有利に働くといわれている。
つぎにイチョウ葉エキスについてであるが、イチョウ葉の効用については中国で去痰・鎮咳に使用されたほか、日本でも健胃薬として使用されていた。1960年代、ドイツでイチョウの若返り効果について関心がもたれ、フランス、ドイツ、スイスで盛んに臨床試験が行われ、末梢血行改善効果や大脳の血流改善効果などが明らかにされ、現在ョーロッパでは脳機能障害の改善などに薬として使用されている。
このイチョウ葉より抽出されたエキスの有効成分はギンゴライド等のテルペンラクトンである。これらは脳の血液循環の不全やそれに伴う機能障害、たとえば記憶減退、知能低下などに改善効果があり、ボケの改善にも使用されている。また動物での学習能力の向上効果も報告されており、※15脳機能を活性化させ集中力を高める効果が期待されている。
以上、三つ(トリプル)の機能素材を配合したガムについて、最近、JR総合研究所塚本らと覚醒効果に関する共同研究を実施したので簡単に紹介したい。
試験方法は被験者の表情や挙動の変化から覚醒レベルを評価し、その時点におけるまばたき回数および閉眼(徐波)などの生体情報とを関連づけた覚醒レベルの評価法である。具体的には、上まぶたが下がり薄目状態のもうろうとした表情が観察されたときの覚醒レベルを0として、刺激を受けた直後の覚醒レベルを1としたときの皮膚電位(SPL)、まばたきの回数、徐波の累積時間より関係式を立て、覚醒度合いを数値化する方法である。
21~31歳の男女各5名について、各種ガム咀嚼による効果を調べた結果を図8に示す。図中、覚醒レベル(W)は1に近ければ覚醒レベルは高く、0に近ければ覚醒レベルが低下した状態と判断できる。いずれもガム咀嚼開始とともに覚醒レベルが増加する。とくにトリプル素材配合のガム咀嚼の場合は、咀嚼直後の高い覚醒レベルが持続し、咀嚼後期の30分まで高レベルに維持された。またガム咀嚼終了後も覚醒レベルの維持が認められた。
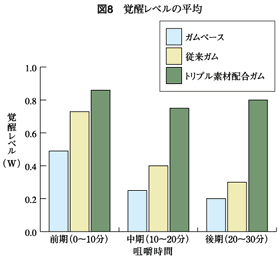
(2)各種効能ガムの素材と機能(2)
口臭は大きく分けて健常者でも認められる生理的口臭、炊食物、嗜好品による口臭と歯周疾患など何らかの疾患により発生する病的口臭、自己臭症の心性口臭に分類される。※17,18 この口臭は呼気とともに口腔内から出る悪臭の総称であるが、すでに口臭に関する一連の研究で臭気物質として、アルコール類、脂肪酸、アンモニア、アミン類、硫黄化合物、フェノール、インドール、スカトールなどが明らかにされている。※17これらの中で、口腔内には多くの蛋白成分や細菌が存在していること、また揮発性や嫌悪性の面から現在では硫化水素(H2S)、メチルメルカプタン(CH3SH)、ジメチルサルファイド(CH3SSCH3)などの揮発性硫化物が注目されている。 ところでチューインガムには元来、歯面清掃効果、唾液の分泌促進、マスキングなどによる口臭を抑制する効果のあることが報告されている。このチューインガムに口臭を除去する素材を添加することにより、より高い口臭除去効果を期待したものが製品化されている。口臭除去をコンセプトとしたこの商品はいつでも手軽に利用できるものとして定着している。 このガムは、現在、緑茶フラボノイドと桑葉クロロフィルのダブル効果に加えて、飲酒後のアルコール呼気臭の低減に効果のあるケンポナシ抽出物を配合し、全体として口臭除去効果を強化した。 これらの口臭除去素材について、まず緑茶フラボノイドから紹介したい。緑茶の消臭に対する効果は先人の経験からトイレの消臭に茶を焚いたり、茶がらをまいて掃除をしたり、台所の臭いを消したりというようなことで利用されており、緑茶と消臭の結び付きは深い。この緑茶から抽出したものが緑茶フラボノイドで、成分的には緑茶特有のカテキンおよび植物体によく見られるフラボノールであるケンフェロール、クェルセチン、ミリセチンなどが存在している。とくにカテキンは緑茶の主要成分であるとともに消臭に対して非常に優れた効果を発揮する。このカテキンはとくに選択的吸着法により茶から分離、精製し、※19その優れた消臭効果を生かしてガムに添加してある。 クロロフィルについては植物から抽出された油溶性の緑色物質で、原料となるクロロフィルは植物全般の葉に分布しており、桑、フェスキュー、コンフリー、蚕糞などを原料として抽出を行っている。工業的に製造されているものは銅クロロフィルとして10~20%程度のものが多い。チューインガムに使用する場合、銅クロロフィルの機能として、単に色素としてではなく口臭除去物質として働いている。 つぎにケンポナシ(Hovenia dulcis Thunb.)に関してであるが、これは北海道から九州、朝鮮半島、中国の広い範囲に分布するクロウメモドキ科の植物である。樹高15~20mの落葉高木で、果実の付いた果柄部は初冬になると肥厚し、肉質となって甘味を生じ、生食することができる。※20古来より、「果柄部を煎じて服用すれば、酒毒を解し、嘔吐を止める作用がある」といわれ、※21酒酔いの解消に利用されてきた。しかし、アルコールを摂取した生体に及ぼすケンポナシの影響について科学的に研究した報告例はなく、近年になってようやく、酒井ら※22により、ケンポナシの熱水抽出物にアルコール投与ラットの血中アルコール濃度を低下させる効果のあることや、永井※23らにより、アルデヒド脱水素酵素欠損型の被験者に対して、ケンポナシの熱水抽出物に悪酔い防止効果のあることなどが報告された。
最近、著者らはケンポナシ抽出物に呼気中のアルコール濃度を低減させる効果のあることをヒトによる試験により確認した。※24ケンポナシ抽出物は乾燥した果実付き果柄部を熱水で抽出し、不溶の夾雑物を除去した後、限外濾過、濃縮、殺菌等の工程を経て調整されたものでグルコース、フルクトース、スクロースなどの糖類の他に蛋白質、ミネラル等の成分を含有している。このケンポナシ抽出物を健康な成人男子8名の被験者に0.125グラム/キログラム体重飲ませて、20分後に0.3グラム/キログラム体重のアルコールとなるように容量を調整したビールを15分間で全量を飲ませた。経時的に呼気中のアルコール濃度を測定したところ、水だけを飲ませたコントロールと比較して、有意に呼気アルコール濃度を低減させた。
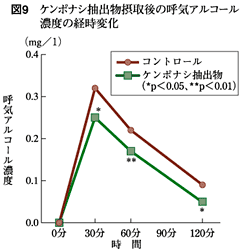
さらに、健康な成人男子を被験者として、ケンポナシ抽出物を含有したチューインガムのアルコール臭除去効果の確認試験を実施した。アルコールとしてビール(アルコール濃度4.5%)、ウイスキー(同43%)、日本酒(同15%)を用い、それぞれ6~8名の被験者にビールでは500ミリリットル、ウイスキーでは50ミリリットル(ミネラルウォーターで四倍量に希釈)、日本酒では180ミリリットルを15分間に一定のペースで飲ませた後、ケンポナシ抽出物含有ガム(ケンポナシガム)またはケンポナシ抽出物を含有しないガム(無添加ガム)を5分間咀嚼してもらった。ガム咀嚼15分後にAlcomed 3010(Envitec社製)を用いて、呼気中のアルコール濃度(ミリグラム/リットル)を測定した。チューインガムの対照として、何も噛まないときのアルコール濃度をコントロールとした。
その結果を図10に示した。無添加ガムではアルコールの種類に関係なく、ガムを噛まないときに比べて、呼気アルコール濃度を低下させたが、とくにビール飲用時には有意な低下を示し、その低下率は17%であった。ウイスキー、日本酒ではそれぞれ7%、6%であった。一方、ケンポナシガムではすべてのアルコール飲料に対して、呼気アルコール濃度を有意に低下させ、ガムを噛まないときに比べてビールでは25%、ウイスキーでは21%、日本酒では28%の低下率であった。さらにケンポナシガムを噛むと、どのアルコール飲用の場合においても、無添加ガムに比べて呼気アルコール濃度を有意に低下させ、その低下率はビールでは10%、ウイスキーでは15%、日本酒では24%であり、日本酒飲用時の低下率が最も大きかった。※25
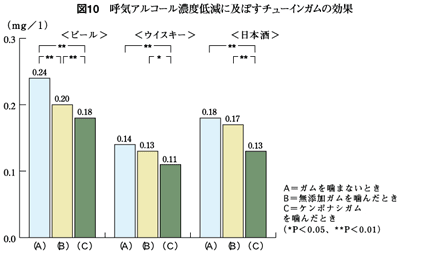
4.参考文献
※1 H.L.Hollingworth・・PsychoDynamic of Chewing,Achives of psychology,R.S.Woodworth.
※2 小野ほか、口腔病学会雑誌 59巻、2号、1992年。
※3 鈴木ほか、日本歯科保存学雑誌、22巷、1号、1979年。
※4 船越ほか、文部省特定研究「咀嚼システム基礎研究」総括班編、17~26頁、風人社。
※5 森本『歯界展望』74巻、1989年。
※6 藤原『歯基礎誌』32巻、1990年。
※7 船越ほか『岐歯学誌』14巻、1987年。
※8 船越ほか『岐歯学誌』15巻、1988年。
※9 松浦ほか『脳の機能とポジトロンCT』秀潤社。
※10 千田「Dental review」『日本歯科評論』、No.620、105~113頁、1994年。
※11 遠藤ほか『交通医学』36巻、1982年。
※12 投石ほか『日本咀嚼学会誌』3巻、1、1993年。
※13 鈴木ほか「Dental review」『日本歯科評論』No.620、85~94頁、1994年。
※14 大久保ほか「日本交通科学協議会、1994年度春期大会講演要旨」79~81頁。
※15 E.Winter:Effects of an extract of ginkgo biloba on learning and memory in mice.,Pharmacol.Biochem.Eehav.,38,109-114(1191).
※16 塚本ほか『日本咀嚼学会誌』4巻、1994年。
※17 角田『歯科学報』76(12)、1923、1976年。
※18 海津ほか『歯科学報』78(7)、1229、1978年。
※19 堀田『野菜茶業試験場研究報告』(金谷)、65、1989年。
※20 村越『薬用植物研究』楊社、1983年。
※21 刈米ほか『和漢薬用植物』176、広川書店、1980年。
※22 Sakai,K.,Yamane,T.,Saitoh,Y.,Ikawa,C.,Nishihata,T‥Chem.Pharm.Bull.,35,4597(1987)
※23 永井ほか「第四五回 日本栄養・食糧学会講演要旨」、168、1991年。
※24 大熊ほか「栄養誌」投稿中。
※25 大熊ほか『日歯心身誌』9巻、2、1994年。